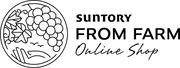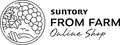皆様こんにちは製造グループの渡辺朋彦です。
早いもので12月になりましたね。いつもの年なら仕込みもとっくに終わりやれやれといったところですが、今年の仕込みシーズンは実はまだ終わっていません。今もまだ貴腐ワインは発酵の途中で終るのは年越しとなりそうです。
さて、ワインは発酵が終わると熟成の過程へ進みます。今回は、現在貯蔵庫で行っている樽熟成への作業についてお話いたします。
登美の丘ワイナリーではフレンチオークの225Lの樽を使用しています。樽熟成の効果は以下の2つです。
1つめは適度な酸化です。樽熟成で生じる変化には微量の酸素が必要であることが一般的に知られており、樽材のオークの微細な木目などから大気中の酸素がワインに供給されます。それはワインに含まれる成分の一種であるタンニンの質の変化を促し、ワインの品質に落ち着きを与えます。空気と適度に触れ合うことによって赤ワインが緩やかにゆっくりと酸素と結合して、渋みの成分である粗いポリフェノール分が落ち、果実の持つ本来のやわらかな旨味が現われるのです。
2つめは樽由来の香味成分の付与による複雑性の向上です。樽との接触によりバニラのような香りや、ココナッツのような香り、スパイシーな香りなどがワインに付与され、複雑な味わいを生み出すことができます。
では、実際にどのような手順で作業を進めていくか。
白ワインは樽発酵させたものを満量にしてそのまま熟成させていきますので、赤ワインについて詳しくご説明します。
赤ワインはステンレスタンク発酵させた後、タンク内でマロラクティック発酵を行ない、そのまましばらく静かにタンクに静置し滓(おり)を沈殿させます。樽詰のタイミングで滓引きを行い、荒い滓とワインを離します。ワインに滓が残りすぎると熟成中に還元臭(硫黄の様な香り)が出やすくなることがあります。逆に滓を引きすぎてワインがキラキラになり過ぎても酸化的になりやすいので注意が必要です。
滓引きしたワインは一度小さな1klタンクに受けてから樽熟庫へと運びます。つい数年前までは写真①の様にタンク上部よりあえて酸素を巻き込むように入れ込んでいました。その理由としては前述の還元臭対策です。還元臭は酸素との接触により減少していきますが、酸素を巻き込み過ぎて酸化的になり過ぎることもワインにとって良くありません。また発酵中の健全な管理によっても還元臭は出さないようにしています。なので現在はタンク下部の飲み口にホースを直接つけ、なるべく酸素を巻き込まないようにしながらワインを入れ込んでいます。
1klタンクに入れたワインをフォークリフトで貯蔵庫まで運んだのち、タンクを写真②の様に高く上げ、落差を利用して樽に詰めていきます。今年の仕込みでは例年よりも手間暇をかけ丁寧な仕込みをしました。粒が潰れず余計な渋みが抽出されずにエレガンスな口当たりの赤ワイン原酒ができています。その原酒に負荷をかけないようにポンプを使用せず自然の落差で樽に入れることで良い効果が期待できます。樽の中で約1年間熟成させ、どのような味わいに変化していくのかとても楽しみです。
あの時のあの対策が良かったのか悪かったのか、答えが出るまではわかりませんが、人事は尽くしたと思っています。
これからもワイナリーでは残りの樽詰めやブレンド、ろ過、瓶詰などまだまだ気の抜けない作業が続きますが、これからも美味しいワインをお客様に届けられるよう引き続き精進してまいります。