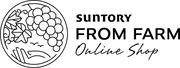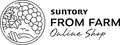「どこのワインが好き?」と質問されたら、皆さんはなんて答えますか?
ビールの好みは、ブランドやメーカーで答えるかも。日本酒の好みは、造り方や味わいで答えるかも。ワインの好みは・・・なんて答えたら良いのでしょう。

「ティピシテ(typicité)」
これは「その土地らしさ、その品種らしさ」という意味のフランス語で、私たち登美の丘ワイナリーが、ワインを通して皆さんにお届けしたいと思っているものです。
造られる土地ごとに違う特徴を持っていることがワインの魅力ならば、その土地ごとの魅力、いわゆる「ティピシテ(typicité)」を知らなくてはもったいない!
そんなわけで、登美の丘の「ティピシテ(typicité)」をすこしだけお話します。

そもそも「日本ワイン」とは何か。
実は、国産ワインの中でも、国産ぶどう100%を使用して国内で製造されたワインだけが「日本ワイン」です。さらに、「登美の丘」シリーズのように、具体的な産地名をラベルに表記できるのは、その地域で育てたぶどうを85%以上使用した場合だけ。
まさに、産地が変われば、風味も変わる、そんなワインの魅力を守り、最大限に伝えていくルールですよね。

「良いワインは、よいぶどうから」
私たちはこの言葉を大切に、ぶどうが育つ畑や土、つまり登美の丘という土地をまるごと大切にしてきました。良いぶどうが育つ環境には、3つの要素があります。
1.昼夜の寒暖差が大きいこと。2.降水量が少ないこと。3.日照時間が長いこと。
(国土の大部分が、降水量が多く、年間を通して温暖な気候である温帯に属する日本がワイン造りには適していない気候風土だと、かつて考えられていた背景です。今では「日本ワイン」は日本の穏やかな気候を反映した穏やかな味わいがすると言われています。短所は長所にもなるものですね!)

登美の丘の立地
登美の丘は、その名の通り、登って美しい丘の上にあります。
富士山をはじめ、南アルプス・甲斐駒ケ岳、八ヶ岳など、まわりを高い山々が囲んでいることによって雨雲が近づきづらく、雨が少なかったり、畑が南向き斜面に広がっているので、日あたりにも恵まれていたり、ぶどうにとっては最高の環境。
 標高も高く、収穫期の昼夜の気温差が10℃以上になる日も多いので、ぶどうはより濃く、甘く育ちます。私たち人間にとっては風邪をひきやすい、甘くない環境ですが、ぶどうにとっては最適なんです。
標高も高く、収穫期の昼夜の気温差が10℃以上になる日も多いので、ぶどうはより濃く、甘く育ちます。私たち人間にとっては風邪をひきやすい、甘くない環境ですが、ぶどうにとっては最適なんです。
 下の写真は1958年頃の山梨農場から甲府盆地と富士山を望むポール式吊棚です。上の写真と比べて比べてみると、登美の丘の変わらない自然に驚きますよね。
下の写真は1958年頃の山梨農場から甲府盆地と富士山を望むポール式吊棚です。上の写真と比べて比べてみると、登美の丘の変わらない自然に驚きますよね。

そのまま食べてもおいしいぶどう
実は、ワイン用のぶどうって食用のぶどうよりも糖度が高いって知ってましたか?
そのまま食べてもおいしい、大切に育てた自慢のぶどうです。
たゆまぬ努力
ここで、「なんだ、登美の丘は何もしなくても恵まれているんだ」と思った、そこのあなた。恵まれた環境に甘えているわけではないのです。
微妙な日照時間や標高差、地形、土壌など様々な条件を考えぬき、ぶどう畑を約50もの区画に分けて徹底した品質管理をして、土壌の改良をしたり、水はけを考慮した排水を考えたりしながら、ぶどうへの愛を惜しまないで徹底的に土を知る努力を続けてきました。
 1909年の開園から1世紀以上の歴史を歩んできた私たち登美の丘ワイナリーは、今でもひとつひとつ丁寧に育てたぶどうを手摘みしています
1909年の開園から1世紀以上の歴史を歩んできた私たち登美の丘ワイナリーは、今でもひとつひとつ丁寧に育てたぶどうを手摘みしています
 ワインに向き合い、ワインの原料であるぶどうに向き合い、ぶどうが育つ畑と土に向き合っている私たちにとっては、今日も、ワイン日和です。
ワインに向き合い、ワインの原料であるぶどうに向き合い、ぶどうが育つ畑と土に向き合っている私たちにとっては、今日も、ワイン日和です。