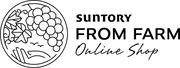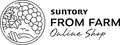日本固有品種であり近年、日本ワインの個性としても注目されているぶどう品種「甲州」について、昨年発表しました「ワインのみらい」の3種の甲州ワインを交えて我々の取り組みをご紹介させていただきます。

「甲州」は、カスピ海の近くコーカサス地方で生まれたヴィティス・ヴィニフェラ種がシルクロードを渡り、 日本に渡来する過程で、中国の野生種(トゲブドウ)と交雑し、再びヴィティス・ヴィニフェラ種と交配したと推測されています。
その歴史は1,000年以上と言われ、シャルドネなどのヨーロッパ品種と比べて比較的病気に強く、高温多湿な日本の気象条件に適したぶどうのため、今では日本における最大のぶどう栽培面積を誇ります。
長く生食用とされていましたが、近年はワイン用ぶどうとして積極的に栽培されていて、特にここ15年くらいで甲州ワインの品質は飛躍的に向上。日本ワインの繊細で上品な味わいを体現した日本を代表するワイン用ぶどう品種となりました。※2010年にはO.I.V(国際ぶどう・ぶどう酒機構)に品種登録されたことにより、国際的に輸出されるワインのラベルに品種表記することが認められました。
100年以上の歴史がある登美の丘ワイナリーでは、歴史のある樹木から若い樹木まで幅広く生育していますが、ワイナリーで栽培されている最古のぶどうは「甲州」で、40年超の古木と、近年になって優良なクローンを選抜し植栽した若木があります。

我々の新しい取り組みとして、つくり手の「想い」や「物語」が見えるワインづくりをコンセプトに昨年リリースした「ワインのみらい」の最初のラインナップの中にも「甲州」があります。
国内でも希少な30~40年の古木から生まれる甲州ワインのじわっと来るおいしさを伝えたい、という想いから生まれた「古木園育ち 甲州」と、2016年から甲州の優良選抜クローンを植えはじめ、年を経るごとに変わる若木から生まれる活き活きとした味わいを楽しんで欲しい、という想いから生まれた「若木園育ち 甲州」は、いずれも、同じ気象条件にありながらこれだけの違いが出る、ワインならではの面白さを伝えたいという想いから生まれたワインです。(通常はこれらのぶどうをブレンドさせた「登美の丘 甲州」をつくります。)

そして、もうひとつ。甲州の9割以上が山梨で栽培される中、この品種の新たな可能性や更なる魅力を冷涼地で広げる挑戦がしたかった、という想いから生まれた甲州ワインが、冬には極寒となる長野県立科町でつくられる「立科町 冷涼地育ち 甲州」です。
畑自体を作り上げるところから始めたこの取り組みは6年越しで実現し、出来たワインは、リッチでありながら、シトラス系の香りを持つ甲州の新境地を切り開いた1本となりました。

栽培技師長の大山はこう言います。
「立科の畑は、ぶどう栽培されていなかったためゼロからのスタート。牧草地を自らトラクターでならし、道路も作り、電柱を立てて電気を引き、事務所も立ち上げて。途中から、仕事というよりライフイベントというか、なんとも言えない感覚になりました。
そんな中栽培を始めたものの、冬は極寒ゆえ1年目の苗はほぼ全滅。諦めずに翌年も植え付けを行い試行錯誤しました。土づくりや仕立の工夫を毎年重ねることで徐々に生育し始め、5年目を迎えた2021年、ついに立派な実をつけました。
ワインになるまで実質丸6年。とても大変でしたが冷涼地の特徴を活かしたぶどうができ、アロマも酸も豊かなワインに。通常、甲州種は熟度を求めると、柑橘系の香りを引き起こすにおい物質が減少するのですが、立科の甲州で造ったワインには、異なるタイプの爽やかな柑橘系のフレーバーがありました。
甲州種は日本でワインを造る意味をとくに強く感じる品種。新たな産地や栽培・醸造方法など、さらなる魅力を探求したい。」
こんなつくり手の想いが詰まった「ワインのみらい」の甲州ワインを是非お試しいただき、樹齢の違い、産地の違いで変わる甲州の多様性を感じていただくと同時に、つくり手たちの想いと物語も味わっていただければと思います。
■本文内でご紹介したワイン
■サントリー甲州ワイン味わいポートフォリオ